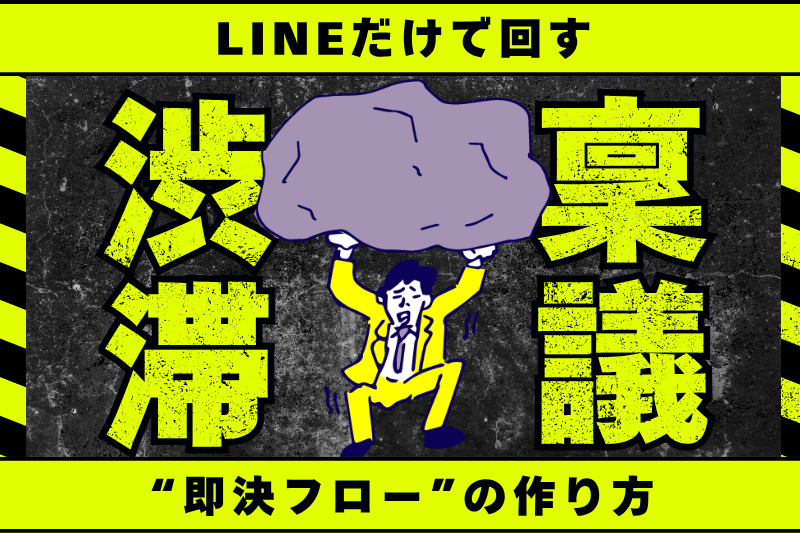「紙の稟議が机の上で渋滞中…」「ハンコ待ちで今日も足止め」――福岡の現場でよく聞く悩みです。全部の制度を作り直さなくても、まずは“LINEだけ”で回せる即決フローを作れば、今日の承認・今日の発注ができます。この記事では、紙と併存しつつスピードは最速化できる設計と、だれでも回せる運用のコツを、福岡の商習慣になじむ形でやさしく解説します。
この記事のポイント
-
紙は残しても即決化
-
決裁の「回覧・押印待ち」を、LINEでの定型投稿とスタンプ承認に置き換えましょう。紙は後追い保管でOKにできます。
-
役割と締切を先に決める
-
起票者・承認者・最終確認、そして締切時刻をテンプレに入れましょう。迷いを無くして即決できます。
-
通知と見える化
-
ピン留め・ノート・タグ(ラベル)で未処理を見える化しましょう。既読だけに頼らず、記録を残せます。
-
小さく始めて広げる
-
1部署・1種類の稟議(少額・定型)から試しましょう。週次で滞留件数を確認し、横展開できます。
-
転記ミスも減らす
-
決裁確定の投稿をそのまま保管名に使い、台帳の入力を型どおりにしましょう。探す・転記を同時に削減できます。
“LINEだけ”稟議の基本設計
目的はスピードの確保です。金額やリスクが低いものは、紙にこだわらずLINEで即決しましょう。紙は「記録用」に回し、意思決定はチャットで完了させます。
役割と締切をテンプレ化(ワークフロー:回覧の流れ)
- 起票者:依頼内容を定型で投稿(テンプレート)します。
- 承認者:スタンプ「承認」または定型返信で可否を返しましょう。
- 最終確認:部長または経理が「確定」コメントで締めます。
- 締切:当日◯時までなど、時間を必ず書きましょう。
福岡の具体例:仕入の小口稟議
博多の飲食チェーンでは、5万円未満の追加仕入をLINEで即決します。起票→店長承認→本部最終確認まで30分で完了できます。紙は週次でファイルに綴じ、監査に備えましょう。
よくある誤解
「既読が付いたから承認」ではありません。既読=承認ではないと明確にし、必ず「承認」スタンプか「承認」と書く定型返信をルール化しましょう。
テンプレートと投稿ルールを作る
投稿がバラバラだと探しにくく、判断も遅れます。書式を一本化し、タイトル(件名)→本文→添付の順で並べましょう。
稟議テンプレ(コピーして使う)
【稟議】件名:◯◯◯(店舗/案件名)
金額:◯◯◯円(税込)
理由:◯◯◯(具体)
必要日:YYYY-MM-DD(◯時まで)
起票者:氏名(所属)
承認者:A→B(順番)
締切:本日◯時/遅延時の対応:翌営業日決裁
添付:見積PDF/写真 等
※承認は「承認」スタンプor「承認」とコメントでお願いします
見える化の小技(タグ:目印)
- ピン留め:当日の未決裁スレッドを必ずピン留めしましょう。
- ノート:週の確定分をノートに一覧化しましょう。
- ラベル(書き出し語):
[未]/[承]/[却]を先頭に付けましょう。
福岡の具体例:工務店の現場発注
現場監督が朝8時にLINEで起票→資材写真を添付→所長が「承認」スタンプ→経理が10時に発注します。午後の配送に間に合い、残業を半減できます。
よくある失敗
- 金額・締切を書かずに雑談スレに流す→誰も判断できず滞留します。
- 承認者が複数なのに順番を決めていない→責任の所在が不明になります。
- 画像だけ送って本文なし→後から検索できず迷子になります。
“即決フロー”の運用手順(今日からできる)
難しい設定は不要です。まずはグループ設計と1日の回し方を決めましょう。
グループ設計(最小構成)
- 稟議グループ:起票者・承認者・経理/総務で構成します。
- お知らせ専用:確定通知だけを流します(雑談禁止にしましょう)。
- バックアップ担当:承認者の代理を1名指名しましょう。
1日の回し方(締切基準)
- 朝:起票→締切時刻を明記→ピン留めしましょう。
- 昼:未承認にはメンションで催促しましょう。
- 締切:最終確認が「確定」コメント→お知らせ専用へ転記しましょう。
- 終業:確定分をノートに貼付→台帳へ入力しましょう。
福岡の具体例:卸売のスポット値引
北九州の部材卸では、スポット値引をLINEで即決します。営業が現場の見積写真を貼り、部長が「承認」、経理が「確定」。顧客の前でその場回答でき、受注率を上げられます。値引理由をテンプレで書くので、後からの説明も楽にできます。
重要ポイント
① 通常のLINEグループだけで始める(最小で早く回す)
まずはスピード優先で、小さく試すやり方です。公式アカウントや外部ツールは不要です。
作り方(手順)
- 稟議グループを作成し、起票者・承認者・経理/総務を招待しましょう。
- 「お知らせ専用」グループを作り、確定通知だけを流しましょう。
- 稟議テンプレをノートに貼り、ピン留めしましょう(誰でもすぐ起票できます)。
- 起票はテンプレで投稿→承認者が「承認」スタンプor「承認」コメント→経理が「確定」コメントで締めましょう。
- 「確定」投稿のスクショ+本文を1つのPDFにし、ファイル名ルールで保存しましょう。
- バックアップ担当(代理承認者)を1名決め、プロフィールに明記しましょう。
- まずは福岡の1部署・1種類(少額・定型)で2週間テストし、決裁時間と滞留件数を測りましょう。
運用ルール(書式の統一)
- スレッド先頭に
[未]/[承]/[却]/[確]を付けましょう。 - 承認はスタンプ「承認」or「承認」の定型コメントに統一しましょう。
- 「確定」コメントは次の形で統一しましょう。
【確定】件名/金額◯◯円/担当◯◯/納期◯月◯日(◯時)チェックポイント(詰まりを出さない)
- 昼時点で未承認がある場合は、@メンションで催促しましょう。
- 締切到達で未承認なら、部長または代理承認にエスカレーションしましょう。
- 長期不在者が出たら、代理承認者を一時的に追加しましょう。
福岡の具体例
天神の小売では、朝9時までに起票→昼12時に締切→13時に「確定」→そのままお知らせ専用へ転記します。午後の搬入に間に合い、残業を抑えられます。
記録と台帳の整え方(紙と監査に備える)
即決でも、あとから説明できる状態にしておけば安心できます。探す・転記の手間も同時に減らしましょう。
保存の型(アーカイブ:保管のこと)
- 確定コメントの直後に、スクショ+テンプレ本文を1つのPDFにまとめましょう。
- ファイル名ルール:
【稟議確定】店舗_件名_YYYY-MM-DD_金額◯◯円.pdfに統一しましょう。 - フォルダ:
/稟議/年/月/店舗の階層で統一しましょう。
台帳入力の省力化
- テンプレ本文の順番=台帳の列順に合わせましょう(転記が一直線になります)。
- 金額と日付は半角に統一しましょう(後の集計が楽になります)。
- 担当者名は略称コード化しましょう(例:
YSK)。
福岡の具体例:月次監査の対応
福岡本社の小売では、月末に「確定PDF」をまとめて経理がチェックします。ファイル名に金額が入っているので、抜き取り検査を約10分で終えられます。紙は月1でプリントして綴じるだけにできます。
よくある失敗
- 確定コメントがばらつく→検索・監査で迷子になります。
- ファイル名が人ごとに違う→月次集計で苦労します。
- 画像だけ保存して本文が無い→理由が追えません。
運用を強くするチェックリストとKPI
「回る仕組み」は点検してこそ強くなります。週次で数字を見て、詰まりを外しましょう。
導入チェックリスト
- 稟議テンプレと確定コメントの書式を全員に周知しましたか。
- 承認の順番と代理者を決め、プロフィールに明記していますか。
- ピン留め・ノート・ラベルの使い分けが定着していますか。
週次KPI(見える化)
- 平均決裁時間(起票→確定までの分)
- 締切超過件数(対総件数%)
- 修正依頼率(却下/差し戻しの比率)
福岡の具体例:数値で納得をつくる
「LINEにしたら早くなった気がする」ではなく、平均決裁60分→18分など数字で示しましょう。社長の納得が早くなり、他部署への横展開も進みます。「即決だけに、ソッと決めていきましょう」。
用語ミニ解説(カタカナ少なめ)
使い分けで迷いがちな言葉を短く整理します。
ワークフロー(回覧の流れ)
だれが、どの順番で、どう承認するかの決まりごとです。LINEのテンプレに順番を書けば運用できます。
テンプレート(定型フォーマット)
毎回同じ形で書くためのひな形です。検索・集計・監査が楽になります。
アーカイブ(保管)
終わった稟議を、後から探せるように保存することです。ノート整理とPDF保管を併用しましょう。
まとめと次にやること
- 金額やリスクが低い稟議は、LINEだけで即決に切り替えできます。
- テンプレ化・締切明記・確定コメントの書式統一で、迷いと滞留を無くせます。
- ピン留め・ノート・ファイル名ルールで、探す・転記の時間を減らせます。
次にやること:稟議テンプレをそのままLINEに貼り、1部署・1種類・2週間でテスト運用を始めましょう。数字(決裁時間・滞留件数)を測って改善しましょう。