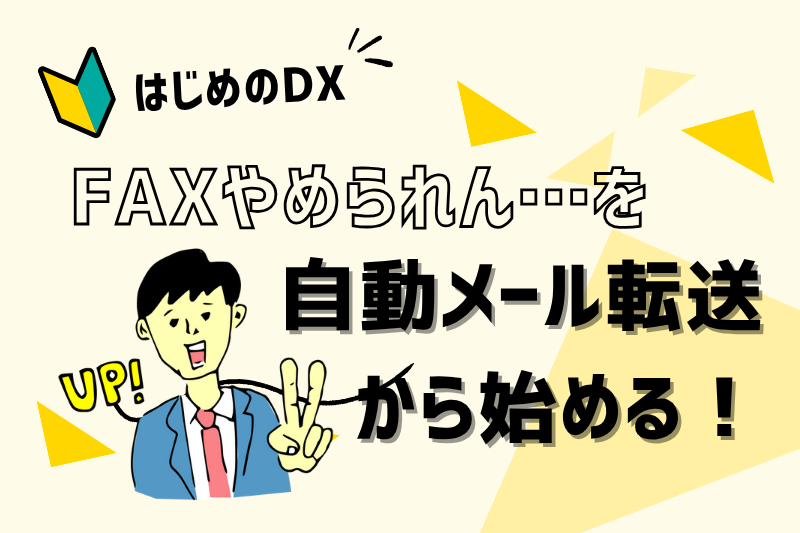「取引先がみんなFAXばい。メール移行は無理…」――福岡の現場でよく聞く声です。無理にやめる必要はありません。まずは届いたFAXをそのままPDFでメール転送できる形にして、「探す・転記」を減らしましょう。この記事では、FAX to Emailの現実的な始め方と、紙のままでも転記ミスをほぼゼロに近づける運用を、博多・北九州の商習慣になじむ形でやさしく解説します。
この記事のポイント
-
やめずに減らすDX
-
FAXは残したまま、受信をPDF化してメールへ自動転送できます。まず「探す・回す」の手間を減らしましょう。
-
選び方の勘どころ
-
番号そのまま運用/PDF化/文字読み取り(OCR)の有無/共有アドレス運用のしやすさで比べましょう。
-
今日からできる設定
-
クラウド型か複合機設定の2ルートで手順を整理します。社内の受け皿(共有メール箱・命名ルール)も用意しましょう。
-
紙のままでもミス削減
-
スタンプやバーコード、スマホ撮影+文字読み取りで「転記」を短くできます。二重チェックは仕組みでなくしましょう。
-
次の一歩が見える
-
週次の数値(探す時間・転記件数・誤記件数)で効果を見える化し、将来のフォーム移行につなげましょう。
なぜ「FAX→メール転送」から始めると続けやすいか
取引先の事情でFAXは残ります。そこで受信ボトルネック(紙を探す・回す・置き忘れる)を先に解消しましょう。PDFで届けば、検索・転送・保管を一気に楽にできます。電話番号はそのままで、現場のフローを大きく変えずに「影の手間」を減らせます。
福岡の具体例:鮮魚卸・工務店・医療材料の現場
例えば鮮魚卸では朝の発注FAXが山のように届きます。PDFメール転送にしておけば、「店名+日付」で検索できます。工務店の見積依頼も、現場からスマホで共有メールを確認できます。医療材料の納入では、発注単価の転記を減らすだけで確認電話を大きく減らせます。
よくある誤解
「FAXをなくさないとDXじゃなかろうもん?」――いえ、“手戻りを減らす”のもDXです。まずは紙を探す時間を削るところから始めましょう。
効果の測り方(探す・転記の短縮)
1通あたりの探す時間(分)/転記にかかる時間(分)/誤記件数で週次集計しましょう。PDF化だけで探す時間が半分以下になるケースが多いです。
FAX to Emailの仕組みと選び方
やり方は大きく2つです。①クラウドFAX(受信を自動でPDF→メール転送)、②社内の複合機でメール転送設定です。どちらも現行のFAX番号を生かして移行できます。
選定チェックリスト
- 番号そのまま使えるか(番号ポータビリティ/転送設定)
- PDF化の品質(白黒・解像度・ファイルサイズ)
- 文字読み取り(OCR:印字を文字として読む)の有無と精度
- 共有メール(例:
fax@〇〇.co.jp)での運用しやすさ(自動振り分け・検索) - 同時受信・混雑時の取りこぼし対策(同時回線・通知)
- 保管期間・ダウンロード制限・アクセス権の付け方
コストと導入の目安
クラウド型は月額固定+従量になることが多いです。複合機設定は機種対応と管理者権限がカギです。まずは1部署・1番号から試すとリスクを小さくできます。
福岡の具体例:本社—支店の“回覧”をやめる
福岡本社にFAXが集中し、支店へ回覧で1日遅れる…あるあるです。PDFメール転送にして、支店の共有メールへ自動配信すれば即日対応できます。回覧用の赤ペンは、メールのフラグとラベルに置き換えましょう。
設定手順:今日からできる最低限
ここでは「クラウド型」と「複合機設定」の一般的な流れを示します。機種やサービスで名称は少し違いますが、筋は同じです。
クラウド型(受信→自動でPDFメール)の手順
- 管理画面で受信先メールアドレス(共有用)を登録します。
- 件名に入れる情報(発信番号・受信日時・ページ数)を設定します。
- 到着通知(到着メール)をオンにします。
- 試験受信:社内のFAXから1通送り、PDFの見やすさと件名を確認します。
- 番号の移行(必要なら)を申請し、切替日を決めます。
複合機でのメール転送設定(一般例)
- 複合機の管理者画面に入り、受信FAX→転送設定を開きます。
- SMTP(メール送信)のサーバ情報・差出人・認証を登録します。
- 転送先として共有アドレスを指定し、PDF添付にします。
- 件名テンプレートに「
【FAX】取引先/日付/ページ数」などを設定します。 - テスト受信→社内で確認→承認後に本番運用へ進めます。
受信後の社内運用:探さない・迷わないの仕掛け
- 共有メール箱を用意(例:
fax@〇〇.co.jp)。個人の受信箱には流さないようにします。 - 自動ラベル(仕入/受注/見積)と担当ごとの振り分けルールを作りましょう。
- 回覧はメールのフラグと未処理ラベルで代替します。
- 保管はクラウドの「案件フォルダ」に日付+取引先で保存します。
件名・ファイル名の命名サンプル
【FAX受信】取引先_案件名_YYYY-MM-DD_頁数3.pdf
【FAX受信】〇〇水産_発注_2025-10-17_2p.pdf
紙のままでも転記ミスを減らす運用
相手が手書きでも大丈夫です。“人が書く”部分はそのままに、“人が迷う”部分をなくす工夫を入れましょう。
二重チェックをやめる仕組み化
- 受信スタンプはPDFの到着メール時間で代替し、重複処理を防ぎます。
- 発注書にバーコード(案件番号)をあらかじめ印字し、受信後にスキャンで案件紐づけできます。
- 不鮮明なFAXは、定型返信テンプレ(「再送願い」)で差し戻しましょう。
スマホ撮影+文字読み取り(OCR)のひと工夫
手書き以外(型番・数量・金額)は読み取り対象にできます。スマホで撮ってOCR(印字を文字に変える仕組み)→表計算に貼り付け→受注台帳へ取り込み、という小さな自動化で転記5分→1分を目指しましょう。
福岡の具体例:納品書の“型”を決める
博多の飲食チェーン向け納品書は、品名→型番→数量→単価→合計の列順だけ統一しても効果が出ます。FAXで届いても、同じ順なら読み取りとチェックを早くできます。
よくある失敗
- メール転送はしたのに共有メールの整備がなく、結局“誰が見る?”問題が続く。
- OCRを万能だと思い、手書きの崩し字で精度が出ずに不満だけ残る。
- 命名ルールが人ごとで乱れ、検索に時間がかかる。
効果測定と次の一手(将来のフォーム移行に備える)
まずは“見える化”の表を作り、改善を回しましょう。FAXが主役でも、裏側でデータが貯まれば次の一手につなげられます。
週次KPI(見える化)の例
- 探す時間の総計(分)/1通あたり平均(分)
- 転記件数と誤記件数(再入力・差し戻し)
- PDFの保存率(案件フォルダに格納された割合)
段階的にやめる作戦
- FAX→メール転送で「探す」をゼロに近づけます。
- よく出る定型の注文は簡易フォーム(QR付き)を案内しましょう。
- フォームが増えたら、FAX分はOCRで補完して集計を一本化します。
まずは小さく試す
「仕入」「受注」など1業務・1番号・2週間でテストしましょう。うまく行けば横展開、だめならやり直しやすい。焦らず、でも止めずに進めましょう。ダジャレで締めると、「FAXだけに、焦(ファ)らんで(ックス)」。…すみません、40代向けサービスです。
チェックリスト(導入前後)
導入の成否は準備8割です。下のチェックで漏れを防ぎましょう。
導入前
- 共有メールアドレスを作成し、閲覧権限を設定できていますか。
- 件名テンプレートと保存フォルダの命名ルールを決めましたか。
- 番号移行や転送の切替日を関係者に周知しましたか。
導入後(1〜2週間)
- 探す時間が半減していますか(実測)。
- 誤記・差し戻しが減りましたか(件数)。
- 未処理ラベルの運用が定着していますか(滞留ゼロ)。
まとめと次にやること
- FAXは残しても、PDFメール転送で探す・回すを先に削減できます。
- 選び方は「番号そのまま」「PDF品質」「OCR」「共有メール運用」が柱です。
- 紙のままでも、命名・ラベル・OCR・バーコードで転記ミスを最小化できます。
次にやること:共有メール(fax@〇〇.co.jp)を作成し、件名テンプレと保存フォルダの型を今日決めましょう。準備ができたら、1番号・2週間の試験運用を始めます。