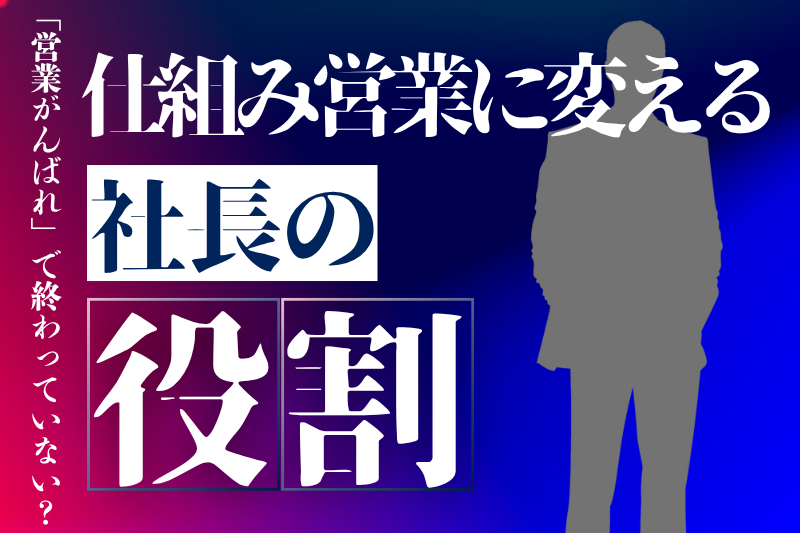会議の締めが「営業、もっとがんばって!」で終わっていませんか? 気合いは大事。でも毎月の数字は仕組みで安定させられます。この記事では、中小企業の社長が主導して「人頼みの営業」から「再現できる営業」へ切り替える道筋を、むずかしい言葉抜きで具体的に解説します。明日から動ける小さな一歩まで、しっかりまとめました。売上アップと補助金活用、二輪で回していきましょう。
-
がんばり頼みの限界
-
個人技に寄るほど波が出ます。休み・退職・季節要因で売上が不安定に。山笠みたいに一瞬は盛り上がっても、担ぎ手次第では続きません。
-
社長の3つの役割
-
方針と指標、顧客情報の見える化、型づくりの推進。この3点を社長が決めて前に進めます。ここを握れば売上アップの速度が上がり、補助金活用の判断もスムーズです。
-
道具は“使い道”から
-
SFA(営業の見える化を助ける道具)やCRM(顧客台帳のしくみ)は、目的→運用→設定の順で選びます。導入費は補助金の対象になることもあるので、最初に確認しましょう。
-
今日からの一歩
-
30日で「共通トーク」「訪問記録」「週次レビュー」を整えます。小さく始めて回します。商店街の朝市みたいに、コンパクトでも回数で効かせるのがコツですよ。
-
定着のコツ
-
数字だけでなく行動も褒める、会議は短く回数多め、仕組みの棚おろしを月1で行います。軽く保てば続きます。
なぜ「がんばれ営業」が限界になるのか
属人的な営業はスピードは出ますが、会社としての再現性が弱くなります。「誰がやっても同じ手順・同じ物差しで動ける」状態を作ることで、採用や育成も楽になります。まずは限界ポイントを押さえましょう。ここを押さえるだけでも売上アップの土台ができます。
よくある誤解:数値目標だけで十分
売上目標だけでは日々の行動に落ちません。「商談数」「初回接点数」「提案数」などの行動指標が必要です。行動が決まると、日々の優先順位がそろいます。屋台の段取りと同じで、並べる順番を決めると回転が上がります。
具体例:地元の卸×飲食向け販売
例えば福岡の食品卸では、繁忙前の月に「新規試食提案10件」「既存先の棚替え提案5件」を週次で確認します。担当者の経験に頼らず、誰でも同じ打ち手で回せます。結果、季節要因の波がゆるみ、売上アップの坂をじわっと登れます。
よくある失敗:記録が続かない
入力欄が多すぎると三日坊主になります。最初は「訪問目的」「要点」「次の約束」の3つだけに絞りましょう。まずは続けることが勝ちです。
仕組み営業の全体像と社長の3つの役割
仕組み営業は「方針→見える化→型づくり→振り返り」の循環で回します。社長が初速をつけ、現場が改善を重ねる形にします。車輪は二つ、売上アップと補助金活用。上手に噛み合わせましょう。
役割1:方針と指標を決める
「どの客層に、どんな価値を, どの順番で届けるか」を一言で言えるようにします。指標はKPI(追いかける途中の数字)を3つまでに限定しましょう。これだけで会議の迷いが減ります。
チェックリスト
- 理想顧客像が1文で言える
- KPIが3つ以内で定義されている
- 週次で見る会議体が決まっている
役割2:顧客情報の見える化を進める
CRM(顧客台帳のしくみ)とSFA(営業の見える化の道具)を導入します。まずは既存の表計算でも構いません。重要なのは「全員が同じ台帳を見て話す」ことです。導入時は補助金対象になりやすいので、費用対効果と合わせて検討しましょう。
用語ミニ解説
- CRM:名前・連絡先・取引履歴を一元管理する台帳の仕組み
- SFA:商談の進み具合や次の行動を見える化する道具
役割3:型をつくり回す
共通トーク(最初の3分の話し方)や提案書のひな形を用意します。「次にどうするかが迷わない」状態を作りましょう。新人さんでも同じ結果に近づけます。
型の例
- 初回ヒアリングの質問10項目
- 見積もりテンプレートと送付文
- 失注理由の選択肢リスト
BtoB向けKPIの具体例(業種別)
「結果目標(売上)」だけだと日々の動きに落ちません。BtoBでは「初回接点 → 商談 → 提案 → 受注 → 継続」の流れごとに、行動と率をKPIに分解しましょう。以下は業種別のたたき台です。自社の商流に合わせて言い換えて使えます。数字は屋台の仕込みと同じで、前倒しが命ですよ。
製造業の法人営業
部品・資材など「サンプル評価→小口→量産」の段階がある前提です。
- 新規初回接点数(電話・紹介・展示会後の一次接触)
- 技術打合せ化率(初回接点 → 技術打合せ)
- サンプル採用率(打合せ → サンプル評価採用)
- 量産移行率(サンプル採用 → 量産発注)
- 平均案件粗利率(見積ベース)
数式の例
- 月受注件数 = 新規初回接点数 × 技術打合せ化率 × サンプル採用率 × 量産移行率
- 月売上 = 受注件数 × 平均受注単価 × 平均粗利率
SaaS/ITツール(法人向け)
無料お試し(トライアル)と継続(解約率)が肝です。SaaS(必要な機能を月額で使う仕組み)。IT導入補助金の対象になり得る領域なので、導入コストは最初に確認しましょう。
- リード獲得数(資料請求・セミナー申込)
- 商談化率(リード → デモ)
- トライアル開始率(デモ → 無料お試し)
- 有料転換率(トライアル → 課金)
- 月次解約率(当月解約数 ÷ 期首契約数)
- ARPA(月あたり平均売上/社)
受託開発/コンサル
高単価・長期案件が多いので、前段の「要件整理」までをKPI化します。ここでの精度が後工程の利益を決めます。
- 案件紹介数(紹介・公募・相見積の招待件数)
- 要件定義受注率(一次面談 → 有償/無償の要件定義合意)
- 提案採択率(提出提案 → 採択)
- 平均案件単価・平均工期
- リピート率(納品後6か月以内の再発注)
建設・設備保守
点検や見積からの「保守契約化」で安定します。施設系の省エネ投資は補助金と相性が良いので、並走できると強いですよ。
- 点検訪問数(安全・法定点検の実施数)
- 見積提出率(点検 → 見積)
- 受注率(見積 → 受注)
- 保守契約化率(単発工事 → 年間保守契約)
- 回収日数(請求 → 入金までの日数)
人材紹介/BPO
「企業側の案件確保」と「候補者側の面接化」が両輪です。商店街の表と裏口、どちらも開けておきたいですね。
- 求人案件獲得数(新規・継続)
- 推薦数(求人1件あたりの推薦数)
- 面接化率(推薦 → 面接)
- 成約率(面接 → 入社/受託開始)
- 定着率(入社後3か月継続)
具体例:福岡の金属加工メーカーの場合
地場の装置メーカー向けに営業する想定です。数字は目安です。
- 新規初回接点数:月30件(展示会後の追客+紹介)
- 技術打合せ化率:40%(月12件)
- サンプル採用率:50%(6件)
- 量産移行率:50%(3件)
- 平均受注単価:120万円、平均粗利率:30%
チェックリスト:KPIが“動きを決める”状態か
- 各KPIに「誰が・いつ・どこで入力するか」が決まっている
- 週次で「未達の一本(率 or 数)」に対する打ち手が1つ決まる
- 展示会・紹介・Webなど、入り口別の「商談化率」を見ている
- 「率」だけでなく「分母(件数)」の目標も置いている
よくある失敗と回避策
- KPIが多すぎる:最大でも3〜5個に整理します。見ない数字は捨てましょう。
- 入力が続かない:最初は必須3項目(目的・要点・次の約束)に絞り、音声メモやスマホ入力を活用します。
- 率だけ追う:分母(接点数)を上げる打ち手(紹介スクリプト・展示会後フォロー)とセットで運用します。
用語ミニ解説(おさらい)
- ARPA(平均売上/社):1社あたりの月額売上の平均
- 解約率:その月に解約した契約数 ÷ 月初の契約数
- 転換率:前工程から次工程に進んだ割合(例:商談→提案)
今日から始める30日プラン
大掛かりな改革は要りません。30日で回せる小さな仕組みから始めましょう。やってみて合えば拡張、合わなければ見直し。軽やかにいきたいですね。
手順:週ごとの進め方
- 1週目:理想顧客像とKPIを3つ決める。既存台帳を一つに集約。
- 2週目:共通トークとヒアリング10項目を作る。提案テンプレも用意。
- 3週目:訪問記録の必須3項目で入力開始。週次レビューを15分で実施。
- 4週目:数字と行動のズレを修正。入力欄を1つだけ増やすなど微調整。
チェックリスト
- 訪問目的・要点・次の約束が全件に入っている
- KPIの未達要因が言語化できている
- 次週のアクションが担当者別に1つ以上決まっている
道具の選び方:名前より運用
有名かどうかより、使い方が決まっているかが大事です。たとえば「外回り中心ならスマホで簡単入力」「見積作成が多いならテンプレ連携が得意」など、現場の一番の不便から選びましょう。福岡の取引先回りが多い会社なら、移動中に音声でメモできるかを重視します。導入費やカスタマイズ費は補助金の対象になり得るので、ここも併走して検討すると費用対効果が上がります。
現場が動く「伝え方」と会議設計
仕組みは「やらされ感」を生むと続きません。短く・分かりやすく・褒めるで回しましょう。商店街の寄合いもサクッと決めてサッと散るのが吉です。
会議は短く回数多め
週1回15分で「先週の良かった行動」「今週の重点3つ」だけを共有します。数字は事前に見られるよう共有し、会議では原因と次の一手に時間を使います。無駄を削れば、売上アップの時間が増えます。
任せ方:最初の成功体験を作る
まずは1チームで小さく始め、成功例を社内で見学できるようにします。新人さんでも同じ結果に近づけるよう、トークと資料を共通化します。型が回りだすと、補助金の申請要件(取組内容・効果)も説明しやすくなります。
インセンティブは行動にも
受注だけでなく「新規初回訪問の達成」「提案の改善事例の共有」など行動も評価します。文化として根づきます。山笠の流れのように、いい動きが次の人に伝播しますよ。
定着させるためのメンテナンス
仕組みは作って終わりではありません。月1の棚おろしで、不要な欄は消し、足りない欄を足します。軽く保つほど続きます。減らす勇気が利益を生みます。
指標の見直し
KPIが増えすぎたら3つに戻します。見ない数字は思い切って捨てましょう。捨てて空いた時間を売上アップの行動に回します。
よくある失敗:形だけ残る
入力はされているのに活用されない状態です。週次レビューで「記録→次の一手」に必ずつなげましょう。必要なら入力支援ツールの導入も検討し、補助金も合わせて確認します。
まとめと次にやること
- 「気合い」から「型と見える化」へ切り替えると、売上が安定します
- 社長の役割は「方針・見える化・型づくり」の3本立てです
- 最初は入力3項目と週次15分で、小さく速く始めます
次にやること:今週中にKPIを3つに決め、訪問記録の必須3項目をチームで合意しましょう。導入コストやツール選定は補助金の対象可否も一緒に確認すると、資金繰りにやさしいですよ。